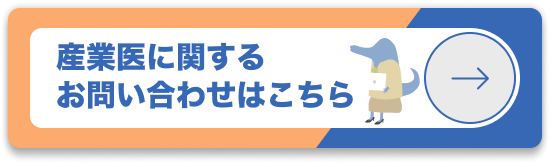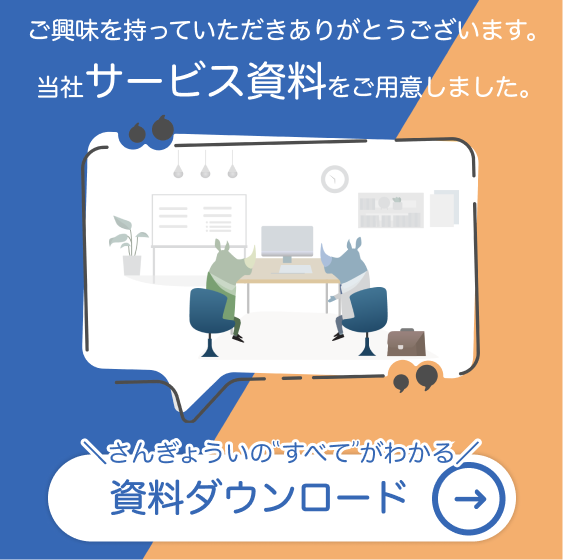第3回: 糖尿病と職場の安全管理

目次
- 働く世代の糖尿病治療で特に注意すべき合併症
- 働く世代の糖尿病治療で特に注意すべき業務・職種
- 安全性に配慮した働く世代の糖尿病治療
- 働く世代で期待される糖尿病治療:GLP1受容体作動薬
- 働く世代の糖尿病治療:食事管理とその実践方法
- 働く世代の糖尿病治療:運動療法とその実践方法
- 産業保健スタッフの役割 (1) - 血糖自己測定、インスリン療法、補食の環境整備
- 産業保健スタッフの役割 (2) - 緊急時対応の体制構築
- 産業保健スタッフの役割 (3) - 主治医との連携 -
- 産業保健スタッフの役割 (4) - 従業員への適切な周知と指導、健康教育
1.働く世代の糖尿病治療で特に注意すべき合併症
糖尿病患者は、重大な二次疾患や合併症が発生しなければ、ほとんどすべての職業や活動を行うことができます。現在では、糖尿病と診断されたからといって、特定の仕事や職業に適さないとすることは許されません。血糖値トレンドの新しい診断方法の導入で、糖尿病のより良い治療が可能となり、仕事上も疾病関連リスクが低減されています。しかし、職業選択の幅が広く活動の変化が激しい現代においては、糖尿病患者の個人能力や合併症の可能性並びに具体的な職業要件を個別に検討する必要があります。
糖尿病の疾病としてのリスクは高血糖による血管障害、神経障害、動脈硬化、易感染性に由来します。それらを列挙しますと、眼合併症(網膜症、黄斑変性、白内障)による視力障害、自律神経障害による起立性眩暈、起立性低血圧による転倒、無痛性心筋虚血や心筋梗塞、重症不整脈による心不全や心停止、膀胱機能低下による尿路感染症、消化管運動機能低下、医原性低血糖による意識障害、末梢神経障害と動脈閉塞による下肢の壊疽、高血糖による血液凝固亢進による脳血管障害、免疫能低下による肺炎、ラクナ梗塞による認知機能低下、糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態など急性の意識障害があります。これらは、リスクの高い様々な業務・職種の労働災害に直結しますので、作業管理、作業環境管理上の配慮事項といえます。
2.働く世代の糖尿病治療で特に注意すべき業務・職種
前述の合併症のある糖尿病では以下の業務・職種には特に注意が必要です。
1) 人または危険物の運輸、運転業務従事者(バス、タクシー、トラックなど)
· 危険性:低血糖による意識障害で重大事故を引き起こす可能性
· 必要な対応:
o 運転前の血糖値チェック
o 低血糖対策としてブドウ糖の常備
o 道路交通法に基づく適切な申告
o 無自覚性低血糖の場合は就業制限の検討
2) 落下の危険性のある高所作業従事者(建設作業員、電気工事士など)
· 危険性:低血糖による意識障害で転落事故のリスク
· 必要な対応:
o作業前の血糖値確認
o単独作業の制限
o低血糖症状出現時の緊急対応手順の整備
o同僚への状況説明と支援体制の構築
3) 睡眠時間が不規則になる交代制勤務者(工場勤務、医療従事者など)
· 危険性:不規則な生活リズムによる血糖コントロールの乱れ
· 必要な対応:
o 勤務シフトに合わせたインスリン投与計画の調整
o 食事時間の確保
o 適切な休憩・仮眠時間の設定
o 血糖値モニタリングの徹底
4) 熱環境作業従事者(調理師、製鉄所作業員など)
· 危険性:脱水によるケトアシドーシスのリスク増大
· 必要な対応:
o こまめな水分・塩分補給
o 定期的な休憩確保
o 体調管理の徹底
o 熱中症予防対策の強化
5) 生命の危険のある職業、警察官・消防士・自衛官など
· 危険性:緊急時対応における低血糖リスク、不規則な活動による血糖調整困難
· 必要な対応:
o 緊急出動時の血糖管理体制の確立
o 装備品への低血糖対策用品の携行
o 同僚への状況説明と支援体制の構築
o 定期的な健康管理の実施
6) 救急医療機関から遠い職場での単独での仕事(保守点検作業員、測量技師など)
· 危険性:救急医療へのアクセスが困難な状況での低血糖リスク
· 必要な対応:
o 単独作業の制限または同行者の配置
o 通信手段の確保
o 救急対応キットの携行
o 作業計画での医療機関アクセスの考慮
これらの職種では、産業医・産業保健師による健康管理体制の整備、主治医との密接な連携、職場での理解促進と支援体制の構築が特に重要です。また、個々の状況に応じた柔軟な対応と定期的な見直しも必要です。
3.安全性に配慮した働く世代の糖尿病治療
一般的に、糖尿病治療を行う際に、血糖コントロールの目標、低血糖リスク、生活パターン、職業上の制約などを総合的に考慮し、患者さんと相談しながら最適な方法を選択することが重要です。糖尿病治療ガイドラインを基に、糖尿病の治療と仕事の両立支援を考慮した場合、以下の段階的治療法選択が提案されます。糖尿病治療法の選択は、膵臓からのインスリン分泌能の低下に従って第1段階から第4段階へと選択します。
第1段階:初期の糖尿病でインスリン分泌能が軽度低下しているが残存している段階です。空腹で服用しても低血糖を起こさない血糖降下薬(DPP4阻害薬、ビグアナイド薬、SGLT2阻害薬)を使用します。前述のリスクが高い危険な仕事に従事する方は、担当医と相談してできるだけ第1段階を選択することをお勧めします。
第2段階:第1段階でコントロールできない場合選択します。インスリン分泌能が中等度低下し、分泌刺激が必要な段階です。スルフォニル尿素薬、グリニド薬を第1段階治療薬に併用します。これらは空腹で服用すると低血糖を起こす血糖降下薬です。多くの場合、この段階での低血糖は自覚症状での判断が可能ですが、危険な仕事の方は、規則的な食事摂取やブドウ糖携帯など低血糖対応が必須です。
第3段階:インスリン分泌能がかなり低下している段階です。第1段階、第2段階の血糖降下薬をそのまま継続して1日1回持効型インスリンを併用します。スルフォニル尿素薬を使用している方は低血糖リスクがあり、危険な仕事の方は朝、夕食事前の血糖測定が必要です。主治医に仕事の危険性を伝え、スルフォニル尿素薬をインクレチン治療に変更することで低血糖を回避することが勧められます。
第4段階:インスリンが高度に低下した段階です。持効型インスリンと(超)速効型インスリン併用で1日4回打ち(強化インスリン療法)と注射頻度が多くなり仕事中の負担が大きくなります。1型糖尿病はインスリンが枯渇しており最初から第4段階を選択します。免疫チェックポイント阻害薬による劇症1型糖尿病、膵全摘後、癌治療などでのステロイド使用例は強化インスリン療法が必要なので最初から第4段階を選択します。近年では、外来通院化学療法が主流となり、この選択が多くなっています。
第3段階、第4段階では自己血糖測定、リアルタイム持続血糖測定(rt CGM : real-time Continuous Glucose Monitoring)が、インスリン療法に限り保険診療で実施可能です(後述)。
4.働く世代で期待される糖尿病治療:GLP1受容体作動薬
第2回でも触れましたが、インスリン治療と新しい治療法についてもう少し詳しく説明します。インスリン治療においては、生理的なインスリン分泌パターンを再現することを目指します。現在では、作用時間の異なる様々なインスリン製剤が利用可能です。厳格な血糖管理を行う強化インスリン療法では、基礎インスリンとして持効型インスリン、食事の際の追加インスリンとして超速効型インスリンや速効型インスリンなどを組み合わせて1日4回の頻回注射を基本とします。
しかし、インスリン治療には以下のような課題があります。
· 仕事中の注射のタイミングや職場での場所の確保が必要。
· 人為的に血糖値を下げるので、食事や労働量で血糖値の変動が大きくなりやすい。
· セルフケアに習熟しないと仕事中の低血糖のリスクが大きい。
· インスリンは脂肪合成作用があり過食により体重増加の懸念がある。
· 頻回インスリン注射は、干渉要因が多いため複雑な仕事との両立の難しさがある。
こういったインスリン療法のデメリットを改善するのがGLP1受容体作動薬です。これは、食事後の高血糖に反応して血糖依存性にインスリン分泌を誘導します。GLP1受容体作動薬が単独では低血糖をきたさず血糖値を低下させ、減量効果があります。インスリン分泌能がある程度残存していれば、各食事の追加インスリンが不要になるため、インスリン注射回数を減らすことが期待できます。また、心筋梗塞や腎不全の予防や治療薬も兼ねるなど多面的作用があります。GLP1受容体作動薬には週1回の注射タイプ、毎朝1回の内服薬タイプ、持効型インスリンとの混合製剤(毎日タイプ、週1回タイプ)などあり、就労状況に合わせて注射療法ができます。最近、週1回の持効型インスリンが開発され、週1回の持効型インスリンと週1回GLP1受容体作動薬の配合注射が開発されています。働く糖尿病患者さんの中には、インスリンの頻回打ちから解放され、職場でのインスリン注射の負担がかなり軽減され、個々の生活スタイルや職業に合わせた、より柔軟な治療が可能になっています。特に働く世代の糖尿病患者にとって、週1回投与の製剤は仕事との両立を容易にし、QOL向上に貢献しています。このように両立支援へ向けて職場と医療機関の情報共有が益々大切になっています。
5. 働く世代の糖尿病治療:食事管理とその実践方法
食事管理は糖尿病治療の基本です。特に職場での食事は、不規則になりがちですが、できるだけ規則正しい時間に摂取することが重要です。国民栄養調査によれば、忙しい毎日を過ごしている現代人のなかには、朝食を食べずに済ませ、昼食まで空腹でいるという人は、20歳から49歳男性は27%、女性17%と少なくありません。朝食を摂らないことは、その後の食事後に血糖値が上昇しやすくなります。朝食を食べない成人は、体重が増えやすく、肥満になる危険性が大きく、2型糖尿病のリスクも高いことが知られています。朝食欠食は、筋肉も萎縮させ、ロコモやサルコペニアの危険性も増大させるという報告もあります。ほぼ24時間の周期で体のリズムを刻んでいる体内時計は、食事のタイミングによっても調整されていることが分かってきました。朝食をしっかり摂る習慣は、体内時計を正常化させ、太りにくい体質をつくり、肥満や2型糖尿病を改善・予防するのに効果的とみられています。
朝食を欠食することの多い人は、仕事が多忙、外食の頻度が高い、インスタント食品の利用が多い、就寝時間が遅い、1人暮らしといった共通する生活スタイルをもっていることが、40~74歳の男女11万人超を対象とした研究で明らかになりました。セカンドミールエフェクトとは、先に摂取した食事(一般的には朝食)が、その後に摂取する食事の後の血糖上昇を抑制するように作用することを言います。例えば、朝食を欠食した場合には、昼食時にセカンドミールエフェクトが生じず、昼食後の急峻な血糖上昇、いわゆる血糖スパイクが生じやすくなることが知られています。このセカンドミールエフェクトは、最初に食べる食事の栄養素バランスによって異なり、高タンパク食を摂取した場合に効果が大きいとする報告があります。このようなことから高血糖を防ぐために、以下の点に注意が必要です。
· 食事時間を一定に保つ:1日3食、特に朝食をしっかり摂る。
· バランスの取れた食事内容を心がける:タンパク質を1回20g以上摂る。
· 必要に応じて補食を適切に取り入れる:不測の低血糖回避する。
糖尿病の実践的食事療法については、公益社団法人 日本糖尿病協会の栄養指導冊子(「糖尿病食事療法の あいうえお」)が参考になります。具体的にはテイクアウト利用術、居酒屋メニューの摂り方、アルコールの摂り方、コンビニ食での食事の摂り方、嗜好品の摂り方、仕事で食事が遅くなる時など記載されています。
6. 働く世代の糖尿病治療:運動療法とその実践方法
1) 糖尿病におけるメリット
長時間座ったまま仕事をするデスクワークや、働き方の多様化に伴い普及したテレワークは、運動不足になりやすいといわれています。運動不足は、心身の健康に影響を及ぼすだけでなく、作業効率や生産性の低下につながりかねません。健康経営や従業員の健康管理が企業の課題となっている現在、従業員の運動不足解消は急務の課題といえます。通勤時の歩行、昼休みのウォーキング、エレベーターの代わりに階段を使用、デスクワーク中の簡単なストレッチにて食事後の高血糖を抑える効果があります。このように、運動は血糖コントロールに効果的ですが、それ以外に、健康的な体重の維持、高血圧・脂質異常症の改善、筋肉量の維持・増加、体の歪みの改善、肩こり・腰痛の予防・改善、血行促進、疲労回復、睡眠効果などのメリットがあります。運動には、気分転換やストレス解消、メンタルヘルス不調の予防に効果が期待できます。運動を行うことで、“セロトニン”と呼ばれる脳内物質の分泌量が増加します。糖尿病はうつ病、うつ状態の合併が多く、自己管理行動、QOLを妨げます。セロトニンは悩みや不安を和らげる働きがあり、“幸せホルモン”とも呼ばれる物質です。そのため、運動を行うと心が落ち着き、集中力が持続しやすくなるため、生産性の維持・向上に貢献します。
2) 運動療法実施時の注意点
インスリン療法やインスリン分泌促進薬の場合には、低血糖になりやすい時間帯があるので注意が必要です。インスリンは原則として、運動の影響を受けやすい四肢は避け、腹壁に注射します。運動誘発性低血糖はインスリン療法やスルフォニル尿素薬使用中の患者に起こりやすく、運動直後でなく運動終了後十数時間後にも起こり得ます。インスリン治療をしている患者は、運動量が仕事で多い時には補食をとる、インスリンを減量するなどの注意が必要です。労働により長靴を使用するときは、フットケアに努め壊疽を誘発しないようにし、大きさなどに違和感があれば職場に伝える必要があります。高温多湿環境での作業や激しい運動は、体温調節機能低下と血糖コントロールを乱す可能性があるため注意が必要です。
3) 運動制限、禁止などについて、以下の場合は主治医に相談することが推奨されます。
· 空腹時血糖値250mg/dl以上の極端に悪い場合
· 増殖前網膜症以上の眼合併症
· 腎不全状態
· 虚血性心疾患で心機能低下や心不全例
· 骨・関節系・腰痛疾患
· 糖尿病性壊疽
· 高度の糖尿病性自律神経障害
7. 産業保健スタッフの役割 (1) - 血糖自己測定、インスリン療法、補食の環境整備

職場における糖尿病患者の血糖測定は、安全な労働環境を確保する上で重要な実践事項です。特に、インスリン治療中の従業員や血糖コントロールが不安定な方には、適切な測定機会の確保と職場での配慮が必要となります。これまで多くの疫学試験から、心血管死を予防するために、HbA1cの値だけでなく血糖値の急激な上昇(グルコーススパイク)や低血糖にも注意を払う必要があることが分かっています。
職場での血糖測定、インスリン注射、補食摂取時の配慮事項として以下の点があります。
· プライバシーに配慮した清潔な場所
· 勤務時間中の血糖測定時間(特に食事前後)
· 血糖測定やインスリン注射、補食摂取のための場所
· 血糖測定器具、インスリンと針の保管と廃棄する場所
· 低血糖対策としてのブドウ糖や糖質含有飲料や補助食品
· 緊急時の対応手順の明確化と関係者間での共有
· 産業医との定期的な情報共有
これらの配慮と情報共有により、糖尿病を持つ従業員が安心して働ける職場環境を整備することが可能となります。
(参考資料:添付PDFおよび日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」)
インスリン療法を受けている人が安全に働くための、いくつかの重要な注意点
インスリン療法を行いながら仕事をしている方には、糖尿病と向き合うポジティブな状態の方もいれば、病気のため不利益を扱いなどで否定的な気持ちの方もいます。また、血糖管理をする上で、現実逃避、体重へのこだわり、低血糖への恐れ、周囲の援助が得られない、将来への不安など様々な葛藤も多いと思います。病気を受け入れるのではなく信頼できる人(上司や同僚)に病気のことを説明する、理解してもらう、支援してもらう、うまく付き合っていくというスタンスが大切です。相談できる相手を早めに見つけること、病気のことを隠さなくてもよい環境をつくること、時間がかかってもカミングアウトすることが大切です。産業保健スタッフは、糖尿病という病気の支援を通して、働く喜びと利益を守り、その方の価値観を守る存在であることを示すことが大切です。ここに周囲や企業への感謝ややる気が出てきますし、貴重な人材の確保になると考えましょう。
8. 産業保健スタッフの役割 (2) - 緊急時対応の体制構築 -
1) 職場での低血糖への備え
低血糖は、臨床的には警告症状と呼ばれるカテコールアミン分泌による症状である手の震えの出現閾値である70mg/dl未満と考えられます。このため80mg/dl未満の血糖値であれば、たとえ症状がなくても補食することが勧められます。一般に1型糖尿病の場合はブドウ糖1g摂取すると血糖値は5mg/dl上がります。ブドウ糖は病院から支給されます。コンビニのお菓子コーナーにブドウ糖のラムネのタブレットがあり携帯に便利です。最近は食品に炭水化物量が表示されておりますので目安になります。また、食事前に低血糖であれば、まず食事を摂取して食後にインスリンを打てばブドウ糖摂取は不要です。意識障害の場合は、歯肉にブドウ糖を直接擦り付けることで、直接血糖値が口腔から吸収されます。最近は、グルカゴンの点鼻薬があり、緊急的に低血糖に対応できます。頻回に低血糖がある場合は、職場に備えておくことが望ましいです。
2) 危険な仕事に際しての低血糖への構え方
糖尿病が長期に及び自律神経障害による無自覚性低血糖の場合は、前駆症状なく突然に意識障害に陥ることがあり、特に、運転や危険を伴う作業に従事する際に血糖測定が必要です。一度、無自覚性低血糖を起こすと、どうしてもトラウマになって高血糖気味にしてしまう場合があります。このような場合は、持効型インスリンを工夫して、最初は目標血糖値を200mg/dlくらいに高めに設定して、少しずつ目標値に近づけていくことで自信が出てきます。低血糖で補食を人前ですることを嫌がり、インスリンを最初から減らす方がいますが、高血糖になり危険です。周囲への理解、説明があれば補食がしやすくなります。
夜勤、激しいスポーツ、海外勤務、運転作業、高所作業など危険を伴う仕事に従事する場合は特に注意が必要です。危険な仕事の前には必ず事前に血糖値をチェックする習慣をつけましょう。
3) リアルタイム持続血糖測定(rtCGM)
近年では、リアルタイム持続血糖測定(rtCGM)の普及により詳細な血糖変動の把握が可能となっています。従来の指先穿刺による測定に比べて正確な血糖管理が可能となりました。一般に、普通の自己血糖測定では24時間の連続した血糖変動を確認することは不可能ですが、rtCGMでは、就労中や就寝中の気が付かない低血糖(無自覚性低血糖)、食後の異常な血糖上昇(グルコーススパイク)、また早朝の血糖上昇(暁現象、ソモジー効果)なども詳しく確認することができます。血糖値の認識が点からパターン認識へと進化しますので、より早めに補食をチャージするなど的確な低血糖対応ができ、仕事場での安全性が向上します。危険な仕事の場合は特に適応があります。現在は、インスリン療法のみに保険適応がありますが自己購入も可能です。
4) シックデイ
体調が悪くなった時(発熱や食欲不振など)は無理をせず、早めに上司に相談し、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。1型糖尿病では食事が摂れないからといってインスリンをすべて中断すると、糖尿病ケトアシドーシスによる意識障害になります。十分な水分摂取により脱水を防ぐこと、口当たりの良い消化の良い食物を選んで、できるだけ絶食しないこと、血糖測定により4時間ごとに測定し、血糖値が高い場合は追加インスリンを打ち、医療機関に連絡することが重要です。
9. 産業保健スタッフの役割 (3) - 主治医との連携 -
仕事と疾病に関する双方の情報共有は、重症低血糖による事故防止や適切な血糖コントロールの維持、緊急時の適切な対応のため不可欠です。特に無自覚性低血糖のリスクがある場合は、連携が必要となります。最初の情報提供の発信は労働者ですが、労働環境の詳細を記載することは困難ですので、産業保健スタッフ(産業医、産業保健師)が協力して作成することになります。医療機関の主治医は、産業医への参考意見とはいえ、就労可否の参考意見を診断書記載の形で求められますので、企業の情報提供は重要です。情報伝達のフォーマットは両立支援ガイドラインや両立支援カードが厚生労働省からインターネット上に開示されておりますのでダウンロードできます。事業所における治療と仕事の両立支援は国の政策として推進されており、別のコラムにて詳細を述べたいと思います。
10. 産業保健スタッフの役割 (4) - 従業員への適切な周知と指導、健康教育 -
このように、糖尿病の管理には、日常生活での継続的な取り組みと、職場環境に応じた適切な対応が求められます。産業医や産業保健師と連携しながら、個々の状況に合わせた管理方法を見つけることが重要です。糖尿病はカミングアウトする義務はありませんが、普段の症状が潜在性でも仕事のリスクに繋がりますので、普段からの職場の理解と協力が必要です。健康教育で糖尿病について職場全体に周知することが望まれます。具体的には次回のコラムにて述べたいと思います。
以上、働く世代の糖尿病治療と職場でのサポート方法を解説しました。
【参考文献】
3) 厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」
4) 労働調査会「産業保健ハンドブック(第七版)」
北海道の拠点病院で糖尿病指導医として勤務。
日々の診療から予防医療の重要さを感じ、産業医も開始。産業医、地方労災医員の活動から診察室と職場をつなぐことの重要性を感じ、これまでの知見をまとめ情報発信を行う。
看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。
現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。