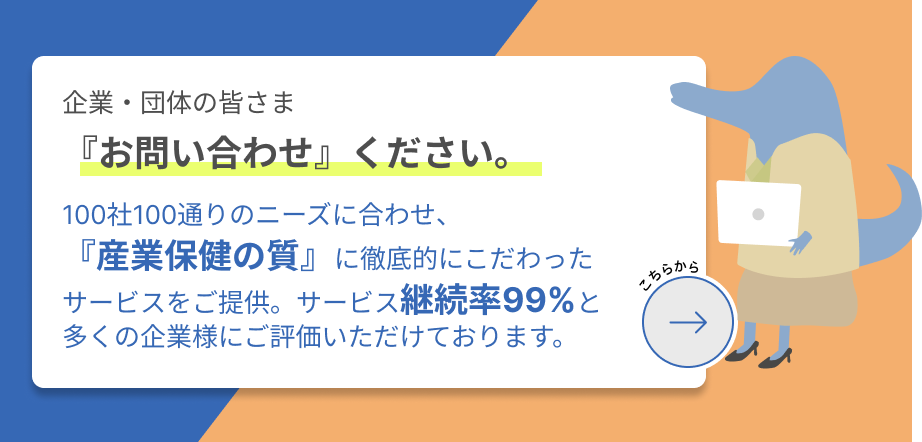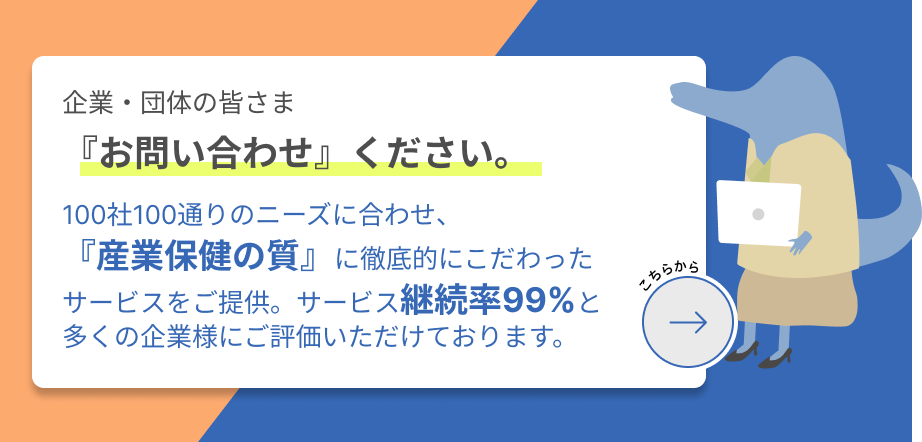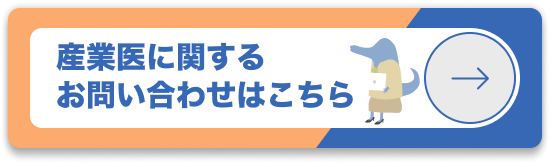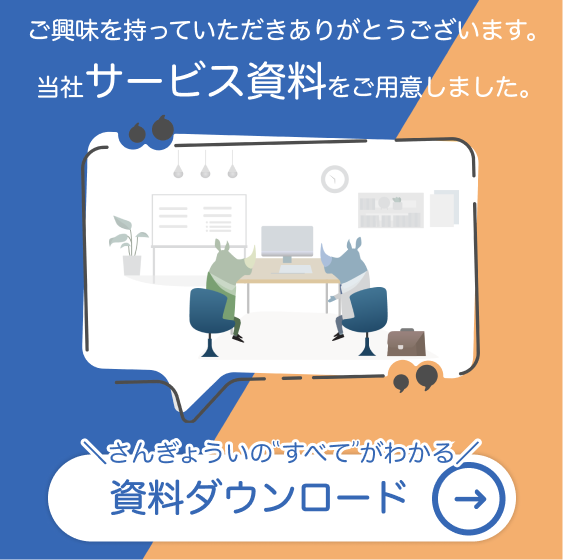健康診断における産業医の役割とは?業務内容や保健指導の重要性も解説

事業者には、安全配慮義務を果たすために健康診断の実施が義務付けられています。そして、従業員の状態を正しく把握して適切な措置を講じるためには、産業医のサポートを受けることが必要です。
健康診断において、産業医は具体的にどのような役割を果たすのでしょうか。今回は、健康診断における産業医の役割や業務、保健指導の重要性などを解説します。
目次
- 健康診断における産業医の役割
- 健康診断における産業医の業務
- 保健指導の重要性
- 産業医による保健指導を拒否する従業員への対処法
- 健康診断の受診を拒否する従業員への対処法
- 健康診断の事後措置に関する注意点
- 健康診断に関するよくある質問
- まとめ:産業医の役割を理解して健康診断を進めよう
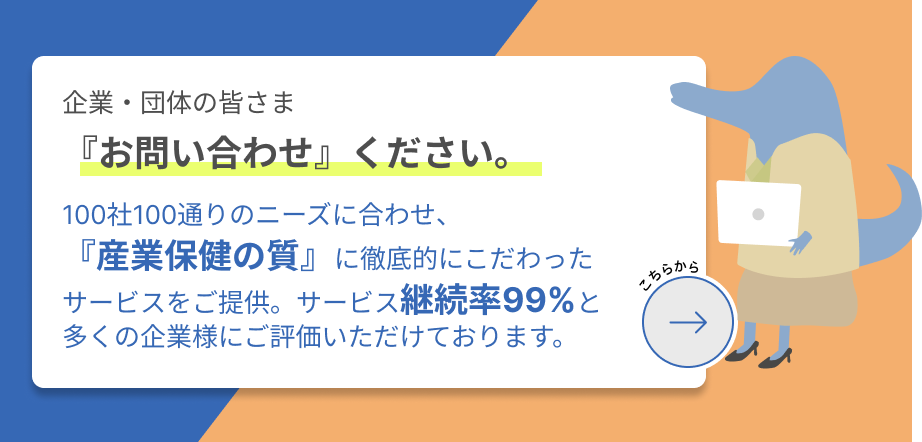
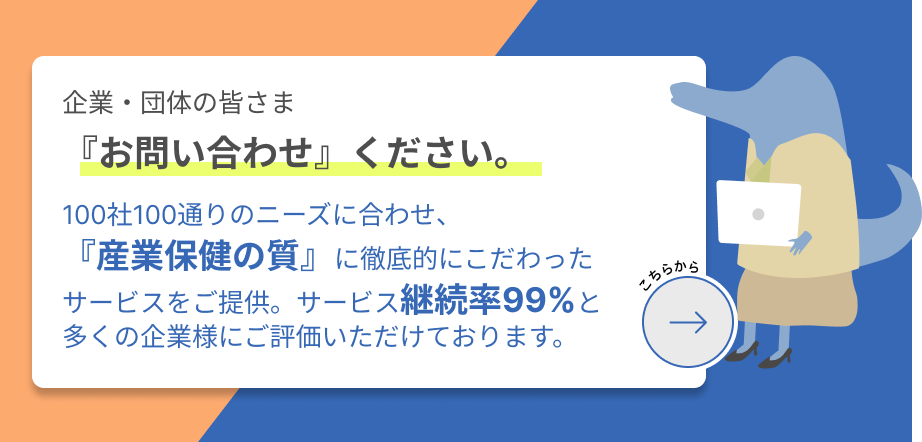
1.健康診断における産業医の役割
産業医は、健康診断の結果から従業員の健康状態を把握し、従業員の健康管理を行う役割を果たします。
具体的な業務は、就業の可否および就業制限や就業禁止などの措置の必要性を判断する、健康状態を改善するための指導を行う、職場環境改善に向けて助言する、などです。
健康診断における産業医の役割の重要性について解説する前に、まずは健康診断そのものの重要性や産業医の役割について見ていきましょう。
健康診断の目的と意義
健康診断は、従業員の健康状態を把握し、従業員を安全な状態で働かせる安全配慮義務を果たすために欠かすことができません。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、従業員に対して医師による健康診断を実施する義務を負います。従業員が1人であっても、健康診断の実施が求められます。
事業者に実施が義務付けられている健康診断は、以下の通りです。
| 一般健康診断 | 対象 | 実施時期 |
| 定期健康診断 | 常時使用する従業員 (特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 |
| 雇入時の健康診断 | 常時使用する従業員 | 雇入れの際 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号で規定される業務(特定業務)に常時従事する従業員 | 特定業務への配置換えの際、6ヶ月以内ごとに1回 |
| 海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6ヶ月以上派遣する従業員 | 海外に6ヶ月以上派遣する際、帰国後国内で業務に就かせる際 |
| 給食従業員の検便 | 事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する従業員 | 雇入れの際 配置換えの際 |
また、有害な業務に従事する従業員に対しては、特別な健康診断を実施することが求められます。
参考:e-Gov法令検索「昭和四十七年法律第五十七号 労働安全衛生法」
参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」
産業医の役割
産業医は、従業員の健康管理を担う医師です。具体的には、以下のような業務を担当します。
- 健康診断の実施や結果に基づく措置
- 長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導
- 労働環境の維持・管理
- 従業員への健康・衛生教育
- 健康障害の原因の調査と再発防止のための措置
産業医学に関する専門知識を持った産業医は、事業者が従業員の健康障害を防止し、健康管理を効果的に行うために重要な存在です。
常時50人以上の従業員を使用する事業場には、産業医の選任が義務付けられています。従業員数が50人未満の事業場については、選任義務はありません。しかし、医学に関する専門知識を有する医師等に、従業員の健康管理等を行わせることが努力義務とされています。
参考:厚生労働省「産業医について〜その役割を知ってもらうために〜」
2.健康診断における産業医の業務

健康診断における産業医の主な業務は以下の通りです。
- 従業員への就業上の措置に対する助言
- 健康管理に関する指導(必要に応じて保健師等と連携)
- 健康診断結果の確認・評価および助言
ここでは、それぞれの業務について見ていきましょう。
従業員への就業上の措置に対する助言
産業医は、健康診断の結果をもとに、従業員の就業に関する適切な措置について事業者へ助言を行います。
事業者は、健康診断の結果により就業制限や休業が必要と判断された従業員に対し、適切な対応を講じる義務があります。しかし、事業者のみでその判断を行うことは難しい場合があります。
そのため、健康診断で異常所見が認められた従業員の就業に関する措置については、産業医や主治医の意見を参考にすることが望ましいとされています。
具体的には、産業医は健康診断結果を評価し、従業員の就業可否について助言するとともに、必要に応じて労働環境や労働管理に関する意見を述べる役割を担います。
【就業判定】
就業判定とは、従業員の健康状態を踏まえ、就業の可否や必要な措置の有無を産業医が判定することです。産業医は、従業員の健康診断結果をもとに健康状態を評価し、必要に応じて精密検査を勧めた上で、その結果や就業状況を総合的に考慮し、適切な対応を決定します。
就業判定は、以下の3つの区分に分類されます。
| 就業区分 | 区分の内容 | 就業上の措置の内容 |
| 通常勤務 | 通常の勤務でよいもの | - |
| 就業制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の 回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。 |
| 要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため、休暇、休職等により一 定期間勤務させない措置を講じる。 |
【意見聴取を行う期限】
産業医からの意見聴取は、健康診断が行われた日から3ヶ月以内に行う必要があります。
参考:e-Cov法令検索「昭和四十七年労働省令第三十二号 労働安全衛生規則」
健康管理に関する指導(必要に応じて保健師等と連携)
事業者は、健康診断の結果を踏まえ、従業員の健康を保持・向上させるための措置を講じる努力義務があり、その一環として、産業医や保健師による保健指導を適切に実施することが求められます。
産業医は、健康診断の結果をもとに、従業員の健康維持・増進を目的とした保健指導を行い、必要に応じて保健師や医療機関と連携しながら適切な助言を提供します。
保健指導では、産業医や保健師が従業員の生活習慣や健康状態についてヒアリングを行い、食生活・運動・睡眠などの改善策を助言するとともに、健康リスクの低減を図ります。また、健康診断の結果に基づき、再検査や治療が必要と判断された場合には、適切な医療機関への受診を促すことも重要な役割の一つです。
健康診断結果の確認・評価および助言
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、労働安全衛生法に基づき、定期健康診断の結果を記録し、「定期健康診断結果報告書」を作成して労働基準監督署へ提出する義務があります。
この報告書の作成および提出は事業者の責任ですが、記載内容について不明点がある場合は、産業医に相談し、適切な助言を受けることができます。
なお、2020年の改正により、産業医による押印(電磁的記録で保存する場合は電子署名)は不要となり、記名のみでの対応が可能となりました。
参考:e-Cov法令検索「昭和四十七年労働省令第三十二号 労働安全衛生規則」
3.保健指導の重要性
保健指導は、健康診断の結果をもとに従業員の健康リスクを評価し、生活習慣の改善や疾病予防に向けた具体的な助言を行うことを目的としています。
事業者には、健康診断の結果に基づき、従業員の健康を保持・増進するための措置を講じる努力義務があります。その一環として、産業医や保健師による保健指導を適切に実施することが求められます。
ここでは、保健指導の重要性について解説します。
従業員の健康状態改善につながる
産業医や保健師による保健指導は、従業員が自身の健康状態を正しく理解し、適切な生活習慣の改善を行うきっかけとなります。
健康診断の結果を踏まえ、従業員一人ひとりの健康リスクに応じた具体的なアドバイスを提供することで、食生活や運動習慣の見直しを促し、生活習慣病の予防につながります。また、従業員が自主的に健康管理に取り組めるよう、継続的なフォローアップを行うことも重要です。
医療機関の受診を促せる
健康診断の結果「要受診」「要医療」と判断された従業員に対して、医師の立場で医療機関の受診を促せるのもポイントです。
医療機関の受診が必要であることを理解していながら、つい受診を後回しにしてしまうケースは珍しくありません。産業医が専門家の立場から受診の重要性や放置する危険性を説明することで、効果的に従業員へ受診を促せるでしょう。
また、産業医が受診に対する疑問に答えたり、不安な気持ちに寄り添うことで、医療機関を受診するハードルが下がる可能性も期待できます。
生活習慣病の予防と健康リスクの低減
保健指導の目的の一つは、生活習慣病の発症リスクを低減し、健康的な働き方をサポートすることです。
健康診断で高血圧・糖尿病・脂質異常症などのリスクが認められた場合、産業医や保健師は、食事の改善や適度な運動の習慣化を促すことで、病気の予防につなげます。
さらに、メンタルヘルスの観点からも、ストレスが健康に及ぼす影響を考慮し、適切なリラックス法や睡眠改善の助言を行うことも有効です。
適切な保健指導の実施が、従業員の健康維持につながる
適切な保健指導を実施することで、従業員は自身の健康状態を正しく理解し、予防的な健康管理に主体的に取り組むことができます。事業者が産業医や保健師と連携し、継続的に保健指導を行うことで、職場全体の健康意識向上や疾病予防の促進にもつながります。
また、従業員が安心して保健指導を受けられる環境づくりも重要です。産業医には守秘義務があり、指導の際に得た個人の健康情報が上司や人事部に伝わることはありません。事業者はこの守秘義務を周知し、相談しやすい環境を整えることが求められます。
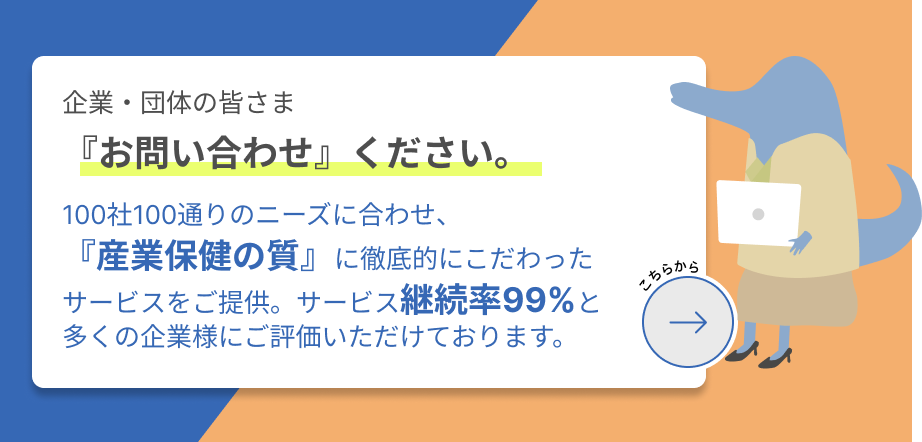
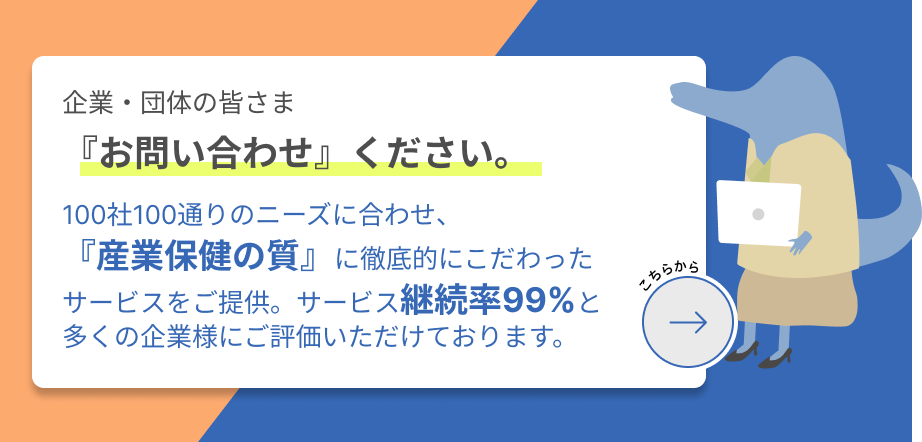
4.産業医による保健指導を拒否する従業員への対処法
産業医による保健指導を拒否された場合は、以下のように対処しましょう。
- 産業医には守秘義務が課せられていることを説明する
- 面談を受けたことや面談の内容によって、従業員が不利益を被ることはない旨を説明する
- 保健指導を受ける重要性やメリットを説明する
- 従業員がリラックスして話せる環境を用意する
- 産業医のプロフィールや人柄を共有する
保健指導を拒否する理由は人それぞれですが、「相談内容が上司や人事部に伝わってしまうのではないか」「指導の結果、不利な扱いを受けるのではないか」「知らない人に相談する勇気がない」といった不安を抱えているケースが多く見られます。
このような不安を払拭し、従業員が安心して保健指導を受けられるような環境を整えることが大切です。
5.健康診断の受診を拒否する従業員への対処法
健康診断の受診自体を拒否された場合は、以下のように対処しましょう。
- 従業員には健康診断を受診する責務があることを説明する。
- 健康診断の結果によって、従業員が不利益を被ることはない旨を説明する
- 従業員の自宅の近くにある医療機関での受診を勧める
健康診断の受診を拒否する従業員の中には、自身の持病や健康リスクが発覚することに不安を抱えている方も少なくありません。このような従業員は、自身のかかりつけ医等で定期健康診断の法定項目を受診して、会社に結果を提出することも認められます。 健康診断の結果によって不利益を被ることがない旨を説明しましょう。
そのほか、健康診断の受診にかかる時間を労働時間とみなし、賃金を支払うのも効果的です。
一方で、労働者にも「労働安全衛生法第69条2項」に基づく自己保健義務があるため、自分の健康を維持することの重要性を理解してもらうことが大切です。
6.健康診断の事後措置に関する注意点

産業医からの意見聴取の後、事業者が事後措置を行う際は、従業員にとって不利な措置を講じないよう注意が必要です。
例えば、以下のような措置は従業員にとって不利益とみなされる可能性があります。
- 健康診断の結果や産業医の意見によって、従業員を解雇する
- 健康診断の結果や産業医の意見によって、従業員に退職を勧告する
- 健康診断の結果や産業医の意見によって、降格等を命じる
- 産業医の意見を聴取せずに、事業者の独断で事後措置を講じる
健康診断に関するよくある質問
最後に、健康診断に関するよくある質問と回答を紹介します。
Q.産業医からの意見聴取では、どのような情報を提供すべき?
A.産業医から従業員の措置や職場環境の改善に向けた意見を聴取する際は、産業医に以下のような情報を提供しましょう。
- 従業員の労働時間、深夜業の回数や時間
- 従業員の作業環境
- 従業員の業務内容や負荷
- 過去の健康診断の結果
また、これらの情報だけでは判断材料として不十分な場合は、労働者と直接面談の機会を設けることが有効です。産業医が職場巡視を実施することも重要です。
従業員の状況や職場環境の実態をもとに意見を述べてもらえるよう、できるだけ詳細な情報を共有してください。
Q.産業医を選任していない場合は、誰に意見聴取や保健指導を依頼すればよい?
A.事業場の従業員数が50人未満で産業医を選任していない場合は、地域産業保健センターを活用できます。
地域産業保健センターは、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する地域の窓口で、小規模事業者や労働者に対し、面接指導の実施、健康相談への対応、産業保健指導の実施などのサービスを無料で提供しています。
サービスを利用したい場合は、事業場を管轄している地域の産業保健センターに問い合わせましょう。
参考:独立行政法人労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」
Q.従業員が保健指導を拒否した場合、どうすればよい?
A.保健指導を繰り返し勧めても拒否する従業員がいる場合は、保健指導を受けるよう促した経緯や、従業員の対応について記録を残しておくことが重要です。
記録を残すことで、事業者が適切な対応を取ったことを明確にすることができます。
ただし、健康診断の結果に基づく指導は従業員の協力なしには実施できません。従業員が積極的に保健指導を受けられるよう 、理解と協力を得るための日頃のコミュニケーションや、健康リテラシーを高めるための教育施策の実施も大切です。
まとめ:産業医の役割を理解して健康診断を進めよう
産業医は、健康診断の結果から従業員の健康状態を把握し、健診結果に異常がみられた際に、従業員に対して二次検査や治療の推奨、生活習慣の改善についての助言をするほか、健診結果の就業判定を行い、就業上の措置に関する意見具申を行います。
特に、従業員の健康管理や病気の予防のためには、産業医による保健指導が重要です。保健指導の実施は義務ではありませんが、従業員が健康的に働ける環境を整えるためにも積極的に実施しましょう。
産業医と事業者が協力して従業員の健康管理を行うためには、自社にマッチした産業医を選任することが大切です。
当社は、産業医選任サポートサービスを展開しています。700名以上の産業医が登録しており、入念なヒアリングを通じて適切な産業医を紹介するのが特長です。また、コーディネーターによる産業保健活動も充実しています。
従業員の健康管理や健康増進を推進したい方は、以下よりお問い合わせください。