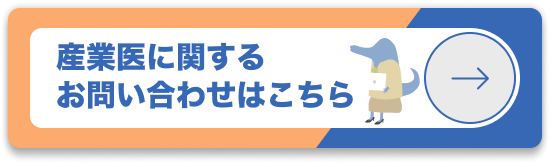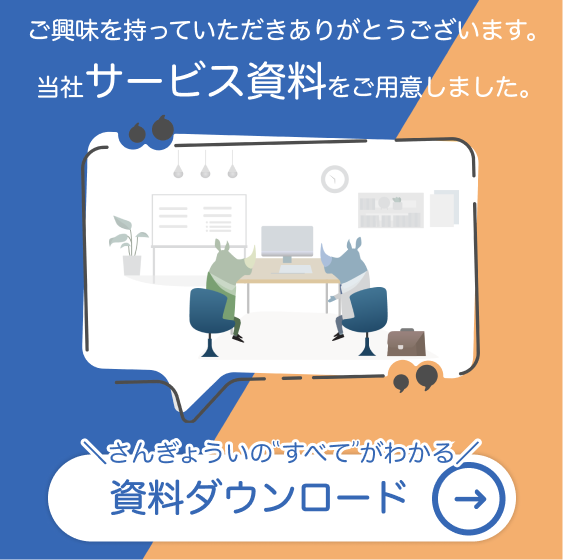第1回: 糖尿病と職場環境の現状

糖尿病は、現代社会における主要な健康課題の一つとして、私たちの生活に深く影響を及ぼしています。この疾患は、血糖値が慢性的に高くなることによって、糖尿病合併症(網膜症、腎症、神経障害)や心筋梗塞、脳梗塞などの動脈硬化症など引き起こす可能性があります。糖尿病は4つに分類され、特に頻度が高いのは2型糖尿病です。遺伝的要因をもとに生活習慣に大きく起因しており、食生活や運動不足、ストレスなどが発症リスクを高める要因とされています。
国際糖尿病連合(IDF)の報告によると、世界中で4億6千万人以上が糖尿病を患っており、その数は年々増加傾向にあります。日本でも約1,000万人が糖尿病患者と推定されており、少子高齢化や定年延長、再雇用の義務化などの影響もあり、治療を受けながら働く糖尿病の高齢労働者が増えています。そのため、糖尿病は個人の健康問題に留まらず、社会全体に大きな影響を与える課題となっています。
当コラムは、全6回でお届け予定です。
目次
1.イントロダクション
1-1 糖尿病の基本的な理解とその社会的影響
糖尿病が引き起こす合併症は、患者の生活の質を著しく低下させるだけでなく、医療や介護にかかる費用の増加によって国や地域社会に経済的な負担をもたらします。糖尿病の管理は公衆衛生上の重要な課題となっています。糖尿病を適切に管理するには、日常的な血糖値のモニタリング、バランスの取れた食事療法、適度な運動療法、そして必要に応じた薬物療法が欠かせません。これらの対策は、患者自身の自己管理能力に大きく依存するため、正しい知識を持ち、継続的に取り組むことが重要です。
1-2 働く世代における糖尿病の増加と職場への影響
働く世代、とりわけ40代以降の中高年層における糖尿病の増加は、職場にとっても大きな課題となっています。糖尿病は、定期的な通院や血糖値の管理が必要となり、それが勤務状況や仕事のパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。例えば、長時間労働やストレスの多い職場環境は、血糖値のコントロールを難しくし、高血糖や治療薬に伴う低血糖を引き起こすリスクを高めます。
厚生労働省の報告では糖尿病を指摘されているにもかかわらず治療を受けていない人は、20-59歳の働き盛り世代で52%に上ります。糖尿病学会の報告では、治療を開始しても8%の患者が途中で治療を中断しており、その主な理由は、「仕事の多忙」51%でした。特に、働き盛りの男性に多いという結果でした。さらに、厚生労働省受託研究結果では、産業医がいる職場でも、要医療、精査の従業員の40%が医療機関に受診を勧められておらず、85%が就業制限受けていません。職場の医療スタッフとの関わりにおいても、糖尿病であることをスタッフが知らない35%、相談できない37%、治療状況を具体的に把握していない49%となっており、職場における糖尿病の治療と仕事の両立支援には、まだ多くの課題が残されていることが分かります。
このような状況において、職場での労働衛生管理の「5管理」(作業管理、作業環境管理、健康管理、衛生教育、総括管理)を適切に実施する産業保健スタッフの役割は、糖尿病対策において極めて重要です。
政府は「働き方改革実行計画」の中で、病気を抱えた労働者が安心して働き続けられる環境を整えるため、職場の意識改革や受け入れ体制の整備、また、治療と仕事の両立を支援する社会的仕組み(トライアングル型支援)の整備も進めています。産業保健スタッフは、職場・外部医療機関・支援ネットワークの連携を促進し、従業員の健康維持と生産性向上を支える重要な役割を担っています。
従業員が健康的に働ける環境を整備するためには、糖尿病に関する啓発活動や教育プログラムを実施し、職場全体での理解を深めることが必要です。また、フレックスタイム制度やテレワークの導入など、柔軟な働き方を推進することで、糖尿病患者がより働きやすい環境を整える工夫も求められます。
2.職場での糖尿病患者の現状
2-1 糖尿病による仕事のパフォーマンスへの影響
糖尿病による高血糖そのものは、直接的に仕事のパフォーマンスに影響を与えることはありません。しかし、慢性的な合併症の進行や、予期せぬ薬剤性低血糖、シックデイ(体調不良時)の急性高血糖などは、職場でのパフォーマンスに大きな影響を及ぼすことがあります。
特に、低血糖になると集中力の低下、めまい、意識障害が生じる可能性があり、安全性が求められる職場では重大な事故につながる恐れがあります。一方、高血糖状態が続くと、倦怠感や疲労感が強まり、持続的な業務遂行が困難になります。その結果、業務効率の低下や欠勤の増加といった問題が発生し、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼします。
また、糖尿病の管理には日々の食事調整、定期的な運動、医療機関への通院が欠かせません。これらを適切に行うためには、業務時間中に医療機関を受診する時間の確保が必要になる場合もあり、職場の勤務時間の調整が求められることがあります。しかし、職場の理解や協力が得られないと、業務遂行がストレスとなり、結果的にパフォーマンスの低下につながる恐れがあります。
2-2 周囲の無理解や偏見について
糖尿病患者が職場で直面する大きな課題の一つに、周囲の無理解や偏見があります。糖尿病は外見からは分かりにくいため、患者が特別な配慮を必要としていることが十分に理解されないことがあります。例えば、定期的な食事や治療のための時間・場所の確保が必要であることを知らない同僚や上司から、不必要なプレッシャーを受けることがあります。このような無理解は、患者にとって精神的な負担となり、場合によっては職場での孤立感を深める原因にもなります。
さらに、一部の人々は糖尿病に対して誤った認識を持っていることがあります。糖尿病は膵臓のインスリン分泌能の低下という遺伝的、疾患的原因がないと発症しません。それにもかかわらず、「自己管理ができないから糖尿病になった」、「自己管理できなかったから合併症が進行した」といった偏見や誤解が存在します。これらの誤解は、患者にとって精神的な負担となり、職場で糖尿病であることを公表(カミングアウト)することをためらう要因になります。カミングアウトをしないことで、必要なサポートを受けられず、リスクを抱えたまま業務を続けざるを得なくなる可能性があります。
職場でのカミングアウトは、患者にとって大きな決断です。カミングアウトすることで理解ある上司や同僚からのサポートを得られることもありますが、逆に偏見や無理解に直面するリスクもあります。そのため、産業保健スタッフは、糖尿病患者が安心してカミングアウトできる職場環境を整えることが重要です。
具体的には、職場全体で衛生教育を実施し、糖尿病に対する理解を深める。患者がサポートを求めやすいオープンなコミュニケーションを促進する。上司や同僚、顧客に対し、糖尿病に関する正しい知識を広める。といった取り組みが求められます。
糖尿病患者が安心して働ける職場環境を整えることは、単に個々の健康を守るだけでなく、職場全体の生産性や士気の向上にもつながります。今後も、糖尿病の治療と仕事の両立を支援するため、産業保健スタッフが積極的に関与し、適切な支援策を講じていくことが求められます。
3.産業保健スタッフの役割

3-1 職場での健康支援の重要性と現状の課題
現代の職場環境では、従業員の健康維持と向上が職場の生産性や持続可能性に直結する重要な課題となっています。慢性的な健康問題を抱える従業員が増える中、産業保健スタッフの役割はますます重要になっています。特に、糖尿病のような生活習慣病は、長期的な健康管理が必要であり、職場での適切な支援が求められます。
産業保健スタッフは、従業員が健康的な生活を送れるようサポートする専門家です。彼らの役割は、従業員の健康診断の実施や結果をフィードバックするだけではありません。健康増進プログラムの企画・運営、職場環境の改善、個別の健康相談対応など、幅広い活動を通じて、従業員が健康的なライフスタイルを維持できるよう支援し、職場の生産性向上に貢献することが期待されています。
しかし、職場での健康支援には、いくつかの課題が存在します。
①リソース不足
多くの職場では、健康支援のための人員や予算が十分に確保されていないのが現状です。このため、産業保健スタッフの数が限られ、従業員一人ひとりにきめ細やかな対応をすることが難しい状況があります。
②健康課題に対する理解不足
従業員自身が健康問題を正しく理解していない場合や、職場内で健康支援プログラムの活用が進んでいない場合もあります。特に糖尿病に関しては、病気の特性や管理方法に対する理解が不足しているため、適切なサポートが提供されにくい状況です。そのため、啓発活動や教育の充実が求められます。
③健康課題をオープンにしにくい職場環境
健康支援の文化が根付いていない職場では、従業員が自らの健康問題を公表することに対して不安を感じることがあります。その結果、必要なサポートを受けられず、適切な治療や管理が難しくなるケースもあります。
これらの課題を解決するためには、産業保健スタッフが職場全体と協力し、職場の健康支援を強化することが不可欠です。
1)経営層や管理職との連携
職場全体で健康支援の重要性を認識し、組織的な取り組みを推進する。
2)外部医療機関や専門機関との協力
社内のリソースが限られる場合でも、外部の専門機関と連携することで包括的な健康支援体制を構築する。
3)従業員の健康リテラシー向上
健康教育や啓発活動を強化し、従業員が自ら健康管理に積極的に取り組める環境を整える。
4)オープンな職場環境の構築
従業員が健康問題を相談しやすい職場文化を醸成し、必要な支援を受けられるようにする。
労働力不足と高齢化が進む中、さまざまな特性や背景を持つ人々が活躍できるダイバーシティ&インクルージョン(Ⅾ&I)推進が求められています。病気の治療と仕事の両立を支援することは、職場の多様性と強みを高める要素の一つです。
・病気と仕事を両立できる選択肢があること
・必要な支援を受けられる環境が整っていること
・産業保健スタッフが両立支援を推進すること
これらが職場の競争力向上にも繋がります。
職場での健康支援をより効果的に行うためには、従業員一人ひとりが健康で活力ある職場生活を送れるようにすることが重要です。そのためにも、外部の医療機関や社会的資源とのネットワークを強化し、職場全体で健康支援をすることが求められます。健康的な職場環境を実現することは、従業員の幸福度の向上だけでなく、職場全体の生産性向上にも繋がると期待されます。
北海道の拠点病院で糖尿病指導医として勤務。
日々の診療から予防医療の重要さを感じ、産業医も開始。産業医、地方労災医員の活動から診察室と職場をつなぐことの重要性を感じ、これまでの知見をまとめ情報発信を行う。
看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。
現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。