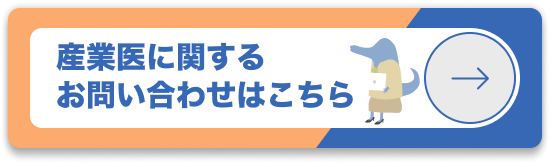押さえておきたい両立支援のポイント 前編

従業員が直面するライフイベントは多岐にわたります。例えば、出産・育児、介護、健康問題、病気治療、不妊治療、学び・社会活動などがあります。
このコラムでは、さまざまな両立支援に共通する基本的なポイントについてご説明します。
目次
1.両立支援のメリット
両立支援は、従業員と企業の双方にとってメリットがあります。
従業員は、仕事とライフイベントを両立することでストレスが減り、健康が保たれます。育児や介護、病気の治療をしながらもキャリアを続けることができ、経済的安定と生活の質が向上します。さらに、柔軟な働き方により、家族との時間も大切にできます。
一方、企業にとっても従業員の健康と幸福は、生産性向上に寄与します。両立支援は優秀な人材の確保と定着に役立ち、企業のブランドイメージも向上させます。適切な支援により法的リスクを回避し、ダイバーシティを推進してイノベーションを促します。
2.法律と企業の取り組み
両立支援に関連する法律には、労働基準法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、次世代育成支援対策推進法、働き方改革関連法など多くあります。近年の法改正により、これらの制度はさらに充実しています。また、企業への助成金などの公的支援も整備されています。
両立支援を推進するためには、まず、これらの法律や公的制度を正確に理解し、企業としての方針を考え、自社の制度を構築し、就業規則に定める必要があります。
しかし、法律に沿って制度を就業規則で定めるだけでは十分ではありません。その理由として、テレワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方の制度が整っていない場合があります。また、規定や制度があっても、本人や管理職がそれを知らなかったり、理解していなかったりするケースも多いです。さらに、企業文化や組織風土が妨げとなり、制度を利用しづらい・利用できない場合もよくあります。
これらの課題を念頭に、両立支援の基本ポイントを次に説明します。
3.さまざまな両立支援に共通する基本ポイント
1.経営者のコミットメント
基本という点では、何にも増して経営者のコミットメントです。
経営者が両立支援の意義を理解し、自分の言葉でメッセージを発信することは、従業員に対する信頼感を高め、共感を得る助けになります。一貫性のあるメッセージが伝わることで、従業員の理解と協力を促進します。また、経営者の明確な支援が従業員の制度利用を促し、安心して育児休業やフレックスタイムを活用できる環境が整います。さらに、企業文化や組織風土に変革をもたらし、柔軟な働き方を支援する文化が育まれます。
一方で、自社の経営者が率先して両立支援に取り組む意思表示ができているかと問われると、「それは、ちょっと…」や「うちの会社では、経営者はあまり関心を持っていない」と困っている方も多いという実態を見聞きします。そのような場合にお勧めするのは、まず従業員の実態やニーズを把握することです。
2.従業員の実態・ニーズの把握
経営者にとって、人材に関する悩みは常に上位を占めます。そこで、アンケート調査などで、従業員が仕事との両立にどんな実態やニーズを持っているのか、生の声を集めて経営者にプレゼンテーションします。そして、両立支援が従業員と企業の双方にどのようなメリットをもたらすかを説明してください。これにより、日ごろから人材について悩んでいる経営者の関心を引くことができます。
また、そもそも従業員調査は、従業員の実態やニーズに合った両立支援施策を考えるためにも必須です。日常において、個人が「私は、両立支援を必要としています」と声を上げることは困難です。しかし、潜在的なニーズは常に存在しますから、調査を行うことで初めてこれほどのニーズがあったのかと気づくことも珍しくありません。
アンケート調査をすると制度を整えなければならなくなるため、実施をためらうことがあるかもしれません。しかし、調査を行わなければ、実態に合った、従業員の満足度が高まる施策にはなりません。
3.柔軟な働き方ができる制度の導入
2024年5月の育児・介護休業法の改正で定められた「柔軟な働き方を実現するための措置等」※は、3歳以上で小学校入学前の子を養育する労働者を対象として新たに追加されたものです。しかし、このような措置を必要としているのは、小学校入学前の子を育てる労働者だけではありません。すでに小学校に入学している子が何らかの事情で親の補助が必要な場合や、親族の介護をしている方、治療しながら働いている方など、自分ではコントロールが難しいライフイベントが理由で柔軟な働き方を望む従業員は多くいます。したがって、従業員のニーズを把握し、それに応じた独自の取り組みを実施することが重要です。
これにより、従業員が自分のライフスタイルに合わせて働ける環境を提供できるようになります。これが従業員満足度の向上につながり、結果として生産性の向上にも寄与します。
もちろん、すべての要望に応えるのは難しい面もありますが、できる範囲で積極的に取り組むことが望まれます。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク等(10日/月)、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与(10日/年)、短時間勤務制度のうち、いずれか2つ以上を選択・措置する。
4.周知と理解の定着
従業員への周知は、形だけではなく、実質的に行うことが重要です。管理職を含めたすべての従業員が両立支援制度の趣旨と概要を等しく理解している状態を目指してください。制度があっても、制度を利用する本人ばかりでなく、その周りの人、特に上司が制度を理解していない事例が多いためです。
上司や同僚が制度の存在自体を知らなかったり、覚えていなかったり、曖昧にしか理解していなかったり、誤解していたりなどのケースをよく見聞きします。
理想は、上司が制度をよく理解し、部下から相談を受けた際に両立方法を両立支援担当者などと一緒に考えることです。できれば、管理職の知識とスキルを向上させるために、両立支援研修を行うことをお勧めします。
5.相談窓口の設置
相談窓口は、従業員が両立支援制度を安心して利用できるようにするために必要です。
例えば、制度の使い方について正しい情報を提供したり、個々の状況に合わせてアドバイスを行ったりします。また、問題が起きたときにすぐに相談できる場所があると、相談者のストレスも減ります。相談窓口には、関連する法律や社内規定に詳しいスタッフを配置してください。
さらに、外部の相談窓口サービスを利用するのもおすすめです。両立支援に関するさまざまな専門サービスを見つけることができます。ただし、外部サービスは社内の事情について詳しくないため、やはり社内の相談窓口も必要です。 これらを整えたうえで、従業員が気軽に相談できるように、場所や連絡方法を明確にし、いつでもアクセスできるようにしてください。
4.おわりに
このコラムでは、さまざまな両立支援に共通する基本ポイントをご説明しました。基本ポイント以外にも、それぞれの両立支援のテーマ別に細かな要点がありますので、それらも漏れなく把握してください。
ご担当者の皆様のご負担は決して軽くありませんが、ここでご説明した基本ポイントを押さえておくことで、両立支援の計画は立てやすくなります。また、実効性も高まりますので、ライフイベントと仕事の両方で従業員の満足度を高めることができます。
継続的な取り組みが、真に働きやすい環境を実現する鍵となるでしょう。
後編では、両立支援において見落とされがちなポイントについて説明します。
【関連記事】「押さえておきたい両立支援のポイント 後編」
管理職として、所属員の病気療養や仕事と育児の両立支援を多く経験。
また、国内外で多くの女性同僚や部下のキャリア形成に携わり、女性特有の健康、ライフイベント、ライフキャリアに深い関心を持つ。